方針
2025年10月21日笑顔は組織のバロメーター
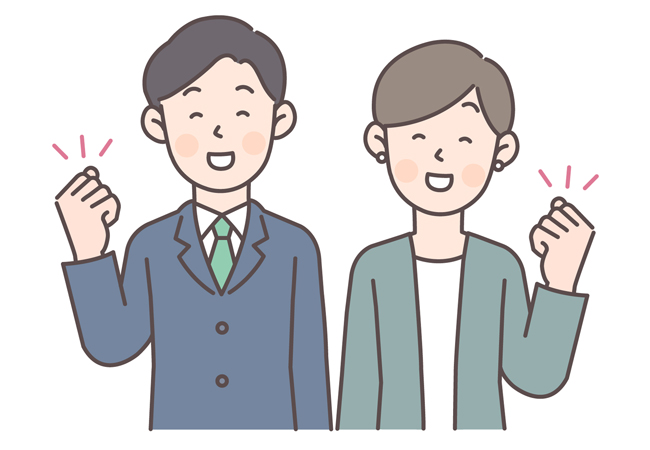
笑顔の方と、気難しい顔をしている方がいるとき、どちらの方が接しやすいでしょうか。聞くまでもありません。ほぼ、すべての方が笑顔の方と答えるように思います。
私が課長の頃、次から次へと降ってわいてくる課題(難題)にてんやわんやすることが多かったと思います。まだ、社会が昭和の名残を引きずっていた時代ということもあり、帰りが深夜ということも珍しくありませんでした。
当時、日常茶飯事的に考え事をしており(そうしなければ物事が進まない)、表情はいつも険しさでいっぱいです。人を寄せ付けるような笑顔はほとんどありません。
「鈴木さん、いつも険しい顔をしていて近寄りがたい」部下や後輩からよく言われたものです。が、当時は、まだ昭和的な考えでいましたから、そう言われるのは仕事に傾注している証であって、むしろ勲章とまで思っていました。
課長は、その課のリーダーですが、リーダーに笑顔がなければ課の雰囲気もピリピリします。ピリピリした雰囲気は必ずしもマイナスということではないとは思っていますが、その雰囲気によって、意見をためらう、委縮するといったことがあると、チーム力としてはマイナスに働きます。
でも、当時は、まだリーダーシップ型の組織運営が主流でしたから、お構いなしでした。もちろん、1人のリーダーよりもチーム力を重視する今の時代にはマッチングしません。
部長の時、トラブル対応が続き組織の中がギクシャクしていたので、解決の一環として対話活動を行った経験があります。対話活動とは、あるテーマを決めて、ざっくばらんに(まじめな)意見を言い合う活動です。お互いが本音で話すことが重要で、そのためには、相手の意見を絶対に否定しない、相手を攻撃(口撃)しない、どんな(賛同できない、えっ!と思うような)意見が出てもこの場限りで引きずらない、などのルールがあります。心理的安全性を確約して腹を割って話す会です。結論は求めず、風通しのよい職場風土作りにつなげるのが目的です。
よりスムーズに対話を行うために、進行役、ファシリテータを立てて行うことが多いです。
1回目の対話活動の際、お互いがそれなりに意見を言い合うことができ、参加した私としても手ごたえを感じていましたが、ファシリテータの総評は「まだ硬い」でした。
2回目のとき、対話活動の中で笑いが起きました。「1回目の時にはなかったいい現象です。」ファシリテータがすかさず宣言します。3回目以降、笑いの数は増えていきました。対話の効果が上がって、メンバーが打ち解けてきた証です。
笑い、いわゆる笑顔の回数は組織風土のよしあしを測るバロメーターということです。
日ごろから、笑顔を心がけるようにしたいものです。心からの笑顔であれば申し分ないのですが、無理やり笑顔を作るのはどうか? 作り笑顔は、口元だけ笑って目が笑っていないなど、何となく相手に伝わります。でも、しかめっ面よりは格段にいいと思います。
なお、作り笑顔でも、笑顔を作るだけで幸福感が得られる効果があるようです。笑顔の表情を作るだけでも、そうでないときに比べて、多くの健康効果が期待できます。笑顔によって脳がだまされるのだそうです。緊張したときも、あえて笑顔を作ることで、緊張が緩和される効果があるとされています。



