方針
2024年08月15日是正処置(対策は原因の裏返し)
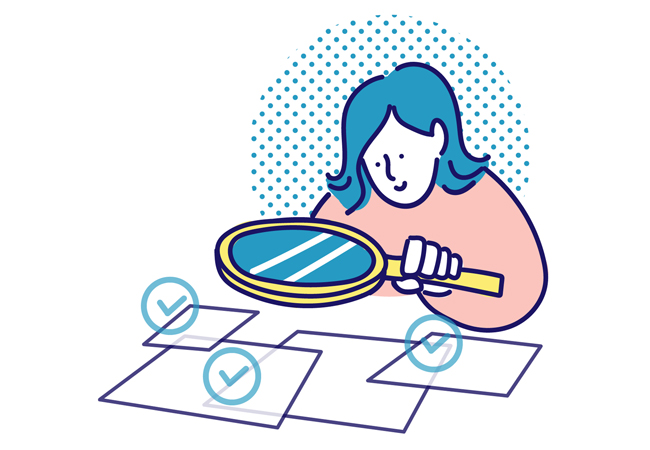
不適合に対し、是正処置という語がよく使われます。是正処置とは不適合の再発防止を行うことを言います。ただ、一般的に「是正する」という言葉は再発防止を指さないことがあります。例えば、書類に誤記を見つけた場合、これを是正するというと誤記を直すことを言う場合が多いです。繰り返しですが、是正処置を行うとする場合は、誤記の原因を追求し対策することで誤記の発生(再発)を防止することを言います。この点は、品証用語に慣れていない方は紛らわしく感じるようです。
是正処置、即ち再発防止のためには、原因を突き止めることが必要になります。先ほどの誤記を例にとると、直接原因は、例えば、ワープロの変換を間違えたとか、写し間違いをして、読み返しのチェックもしなかったということが当てはまります。対策は原因の裏返しなので、例えば、読み返しのチェックをルール化するといった対策になるでしょう。
是正処置には、実効性のレビューが必要になります。一定期間、再発をしなかったかを見る手法が一般的です。先ほどの例では、読み返しのルールを適用して、一定期間(例えば半年間)誤記が発生しなかったら、この是正処置には実効性があったということになります。レビュー期間に誤記が発生した場合(不適合の再発)、その是正処置では不十分であり、新たな原因の追究と対策が必要になります。
不適合の重要度に応じて、直接原因だけではなく、背後要因を追究する必要性が出てきます。先ほどの誤記でも、これが頻発して重要な書類に誤記が発生、規制当局や顧客に迷惑をかけた場合は、背後要因までさかのぼることが必要になるでしょう。この場合はいわゆる「なぜなぜ分析」を行うことになります。なぜそれができなかったのかを5回くらい繰り返して原因と対策を練ります。なぜルールを守れなかったのか→○○だから、なぜ〇〇だったのか→◇◇だから、なぜ◇◇なのか、といった具合に繰り返すわけです。
先ほど、対策は原因の裏返しと述べました。実はこれはかなり重要なので意識していただきたいです。原因と対策が報告される資料を読んでも、裏返しになっていない場合が結構あります。例に挙げると
原因:〇〇課と△△課のコミュニケーションエラーが原因
対策:案件の実施前に〇〇課と△△課で◇◇を確認することをルール化した
一見、よさそうにも見えますが、原因がコミュニケーションエラーで止まっています。その裏返しの対策はコミュニケーションエラーを起こさないことになります。非常に抽象的で何をやっていいかわかりません。ただ、この場合は、対策がもっと具体的になっているので原因の深掘りはできているようです。この場合、コミュニケーションエラーの発生について、実施前に双方の課で確認していなかった、そのルールもなかったとしているようですが、それが隠れてしまっています。なお、この隠れた部分が皆の共通認識になっていない場合が往々にしてあります。その場合は対策の妥当性に疑義を生じることになります。
この例にもあるように、原因の記載が抽象的であるほど、対策の妥当性に疑義を生じやすいということになります。実際、原因が中途半端な場合は、ファクト整理ができていないことが多いです。ファクトを5W2Hで詳細に確認し、そのうえで原因を具体的にあぶり出し、原因の裏返しで対策を導き出すようにしましょう。この点は私が真っ先にチェックするポイントです。



