方針
2024年06月13日アイディアあれこれ その2
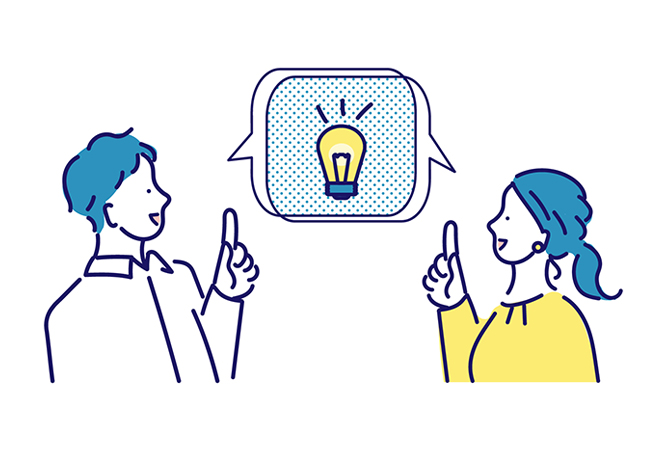
今回は、先日のアイディアに係るブログ(2024.6.11 アイディアあれこれ)の続きに当たる話です。
多忙や不便を楽にするためには、定型的な業務であっても、改善や効率化の余地がないか、それを実現するためのちょっとしたことでも、工夫やアイディアはないかと意識して考えることは大切です。
アイディアは残り物の食材で料理を作る感覚でもあり、既にあるものを掛け合わせたり、別の用途に転用したりすることで、新たな価値が生み出されることがよくあります。無から有を生み出そうと難しく考えるのではなく、そんなやり方でもよいと思いますし、それがありそうでなかったアイディアの本質かもしれません。
そうなると、ものすごく思い付きそうもなしく、とんでもないものがアイディアだと言うよりも、誰もが見たことがあるようで誰も見たことがないもの(当て嵌めたことがあるようでないもの)が理想で、皆に共通する「安心感の領域」で、その境界線ギリギリに接しているようなアイディアを目指せればよいのかもしれません。先ずは、カイゼンや工夫の対象に気づくことも、そんなアイディアを生み出すことも、やはり難しいのですが、そんなアイディアは議論の脱線で生まれることも多いものです。
脳はふだんからリラックスさせ、負担を掛けないことでひらめき体質になると言われます。そこで、解決策を必要とする課題認識と、アイディアを求める意識が大切ですが、案外ルーチンワークや普段の生活の中からアイディアが出ることも多いものです。そんな場合は、生み出したアイディアというよりふと出てきたアイディアという感覚かもしれません。具体的にいつ、どのように出るのかは分かりませんが、意識を高くしている中で自然とアイディアが出ることが理想的ともされます。
しかしながら、自分の中で「これぞ」と思うアイディアこそ、一度放置してみることも意味があります。しばらくして改めて見ると、さらにそのアイディアが発展する可能性が見えてくることもあります。人に話してみることも方法の一つで、かわいい子に旅をさせるのと同様に、かわいいアイディアには旅をさせる感覚とでも言いましょうか。
ただ、アイディアの「鮮度」は意識する必要はあります。シチューのようにぐつぐつと煮込むことで味が出るアイディアもあれば、スパッとお刺身のようにさばいた方が良いアイディアもあります。食材(=アイディア)を見極めてから正しい調理法(=アウトプット)をするように、関係者で議論するようにしたいものです。



