方針
2025年01月23日イエス、ノーを問う質問に対して
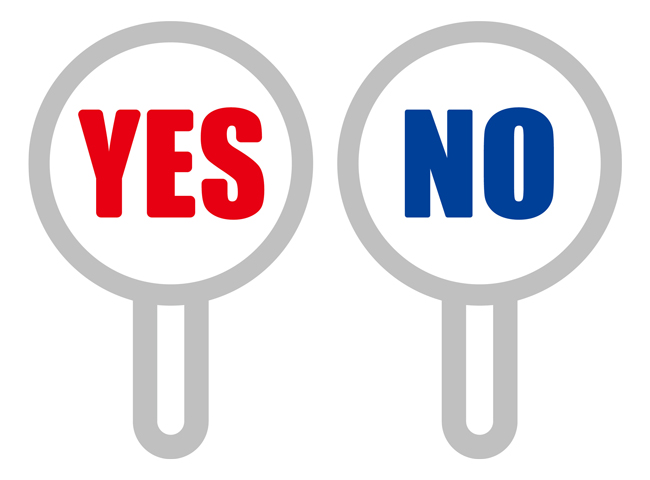
ビジネスの文書では、「概観から細部へ」が重要と述べましたが、これは文書だけでしょうか。日常のコミュニケーションでは文書よりも口頭でのやり取りの方が多いのではないでしょうか。大勢でのコミュニケーションの場では、文書の方が共有化には適していますが、その場合でも、説明や質疑応答は口頭です。1対1のコミュニケーションでは、かなりのケースで口頭が主でしょう。
口頭の場合は、「起承転結」型の説明の仕方で事足りる場合も多いのですが、やはり文書同様、「概観から細部へ」を心がけるべきと思います
特に気を付けたいのは、以下のような相手の質問に対してどう答えるかです。
「計画書にかかれたこの部分はやったのですか? やらなかったのですか?」
過去の事実を問う質問であり、イエスかノーかで答えられる質問です。不具合等の事実確認のときに出てきやすいです。自信をもってイエスと答えられる場合は、即座に「やりました」と返す場合が想像できます。一方、例えば、答える方が不具合を起こしている場合、どこか後ろめたさがあるでしょう。すでに、聞き手/答え手の間には、精神上、対等関係にないといってもいいかもしれません。答え手は、実際にやっていなかった場合、何かと説明をしたいという欲求が出てきます。
「それについては、こうこうこういう状況でかなり業務が集中しており、〇〇さんと△△さんがお互いに自分のテリトリーに集中せざるを得ない状況でした。監督の◇◇さんがその部分を補うことにしていたのですが、当日は体調不良で会社に出られず調整ができませんでした。なおかつ、監督代理の□□さんは、ちょうどその時間帯に別の件名で現場にいってしまい調整ができませんでした。その結果、計画書で行うとされていたこの部分は、できておりません」
聞き手は、やったのかやらないのかを求めています。その結論に達する前に、事情をとくとくと説明されるわけです。起承転結、まさに、エッセンスが末尾に来ます。細部からの説明であり、聞いていてやきもきするでしょう。話の途中で一番関心のある結論がなかなか出てきません。もしかすると話の途中から頭の中で結論を推論しにかかっているかもしれません。そうなると、途中から説明をあまり聞いていない状態になり得ます。どこまで伝わっているかも怪しくなるわけです。短気な方からは、話を遮られるかもしれません。
イエスかノーでの回答を求められた場合は、まずは、イエスかノーかを述べ、そのうえで事情を話す方が、はるかに効率的です。以下の4つのどれなのかをまずは伝えましょう。概観から細部への実践です。
①Yes ② No ③Yes, but ④No, but
今回のケースではこんな感じです。
「計画書のこの部分は、結論から言えばできていません。事情を説明しますと・・・」これで、会話の効率性はぐっとあがります。
なお、同じようにイエスかノーかを問われる質問ですが、「これ、引き受けていただけますか?」のようなお願いごとの場合、将来に対する質問であり、①Yes ② No ③Yes, but ④No, butで竹を割ったような回答ができない場合があります。質問の趣旨・内容によって使い分けることが必要です。



